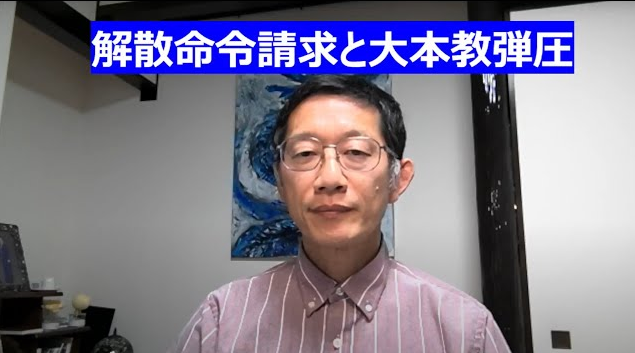要約
この動画では、家庭連合の解散命令請求と戦前の大本教弾圧の類似点について語られている。
大本教の弾圧
大本教は出口直を教祖とする新興宗教で、大正時代から昭和初期にかけて急成長したが、国家から危険視され、二度の大規模弾圧を受けた。
- 第一次大本事件(1921年):教祖の墓を暴かれ、本部の神殿が破壊された。陰謀や武器隠匿の疑いをかけられたが、証拠は見つからなかった。
- 第二次大本事件(1935年):治安維持法が適用され、武装警官500人が踏み込むも、実際には信者は無抵抗で、武器も発見されなかった。逮捕者が出たほか、拷問による死亡者も発生。
- その後、裁判で有罪判決が出たが、最終的には無罪となった。しかし、その間に神殿はダイナマイトで爆破され、多くの信者が苦しんだ。
現在の家庭連合に対する解散命令請求との比較
- 戦前の大本教弾圧は「国家による宗教弾圧」として歴史的に反省されるべき事件だった。
- 2021年、朝日新聞も大本教弾圧を批判する記事を掲載していたが、2022年の安倍元首相銃撃事件後、統一教会(家庭連合)へのバッシングに加担し、過去の宗教弾圧を忘れたかのような対応を取っている。
- 家庭連合の信者は社会を破壊しようとは考えておらず、かつてのように神殿を爆破する代わりに、今は礼拝堂や聖地を奪い去る形での弾圧が進められている。
結論
過去の宗教弾圧から学ばず、同じような国家権力による迫害が繰り返されることは問題であると警鐘を鳴らしている。