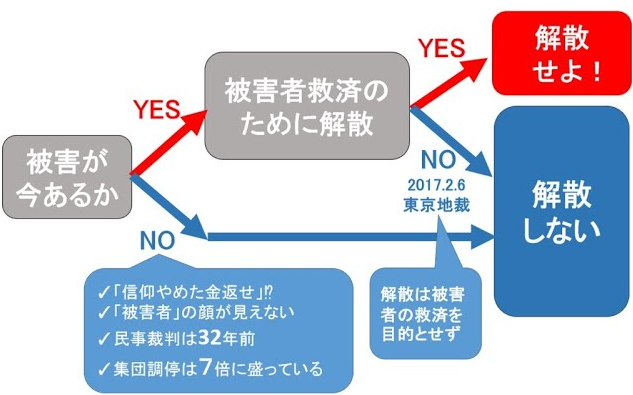家庭連合の解散問題/中山達樹弁護士ブログ川塵録 2025年03月19日
📅 2025年3月19日
🎥 YouTubeリンク
概要(100字程度)
中山達樹弁護士は、家庭連合の解散命令請求に関する問題点を整理。32件の裁判の多くが数十年前の事案であり、被害者の顔が見えない現状を指摘。被害者救済と解散命令の目的が異なることを法的に論じた。
詳細な要約
1. 解散請求の論拠と問題点
- 解散請求の根拠
- 霊感商法被害者救済を目的とするもの
- 「被害があるから解散」という主張のプロパガンダ戦略
- 主な疑問点
- 現在、本当に被害があるのか?
- 「進行をやめたから金を返せ」という訴えが安倍暗殺事件後に急増。
- 事件を契機にマインドコントロールが解けたという主張の矛盾。
- 被害者の顔が見えない
- かつてメディアに登場した小川さゆり氏も現在は姿を消している。
- 顔を出して被害を訴える人物がいない。
- 解散請求の根拠となる32件の裁判
- 平均すると32年前の事案が中心。
- 32年前には**「パワハラ」という概念すらなかった時代の事例**を基にしている。
- ネオ霊感弁による集団交渉
- 調停が増加しているが、訴訟で負けるから調停になっている可能性が高い。
- 献金額が7分の1に減少しており、実際の被害規模は縮小している。
- 現在、本当に被害があるのか?
2. 被害者救済と解散命令の目的の違い
- 解散命令の本来の目的は「治安維持」
- 「被害者救済」のために解散するという論理は本来の法的枠組みと異なる。
- 文科省が2017年の東京地裁判決で「解散と被害者救済は別」と判断されている。
- 家庭連合解散を目的とした文科省の責任追及裁判でも、2017年の東京地裁は解散の正当性を否定。
結論
- 解散請求の論拠は過去の事例に依存し、現在の実態を反映していない可能性がある。
- 被害者救済を理由に宗教法人を解散するのは法的に問題がある。
- 家庭連合の解散命令は、目的と手段の乖離があることを改めて検証すべき。