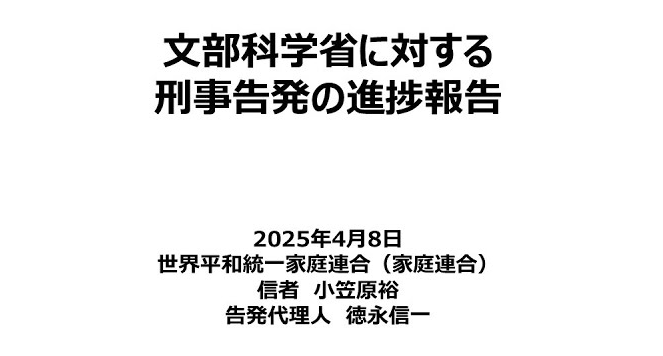要約(概要)
- 解散命令の根拠と推定の問題
- 東京地裁は「不法行為」の成立をもって家庭連合(旧統一教会)の解散命令を認めた。
- 過去の訴訟件数や和解・時短事例から“累計的傾向”を抽出し、「他にも隠れた被害があるはず」として不法行為を推定している。
- コンプライアンス宣言後の被害は大幅に減っているが、裁判所は「根本的に改善されていない」と判断した。
- 行政事件特有の“推定”の働き
- 刑事事件とは異なり、行政行為(文科省)の適法性・合理性がある程度推定される。
- そのため、教団側が「無罪」を立証する(不法行為がないことを証明する)負担が大きくなる。
- 裁判所は「(文科省側の)隠れた被害の存在」の推定を取り下げず、解散命令を正当化した。
- 文部科学省の提出した陳述書の偽造疑惑
- 文科省が裁判所に提出した294件の陳述書のうち、コンプライアンス宣言後の被害を示すため「新たに作成した」18件に多数の偽造が疑われる。
- 例:
- Aさんの陳述書:実際の本人証言と食い違い。
- Bさんの陳述書:書かれた内容を本人が「記憶にない」と証言。
- Cさんの陳述書:現役信者名義だが、本人は「自分は書いていない」と語る。
- 他宗教の信者分まで混在するなど、虚偽や捏造の疑いが強いケースもある。
- 文科省に対する刑事告発の概要
- 家庭連合側は、これら偽造陳述書を「有印私文書偽造・行使」にあたると判断し、文科省担当者らを刑事告発した。
- 告発は東京地検特捜部に送られ、内容の特定(偽造日時や行使日時の詳細)が求められている段階。
- 今後、詳細を補完した再提出を経て「受理→捜査→起訴/不起訴」の判断となる見込みで、長期的な審理が想定される。
- 偽造告発が持つ意義
- 行政事件では文科省など公的機関の行為に「合理性」が推定されるため、それを覆す決定的証拠が必要。
- 偽造・捏造が事実であれば、文科省側の信用性が大きく揺らぎ、解散命令の根拠となる「推定のロジック」を崩せる可能性がある。
- また、家庭連合としても「すでに法令順守に努めており、文科省の主張こそ不当である」ことを証明する狙いがある。
全体として、本件の焦点は「コンプライアンス宣言後の被害実態を示す文科省の証拠の信憑性」であり、その中で陳述書偽造疑惑を刑事告発することで、解散命令の根拠に根本的な疑義を投げかけようとしている状況にある。