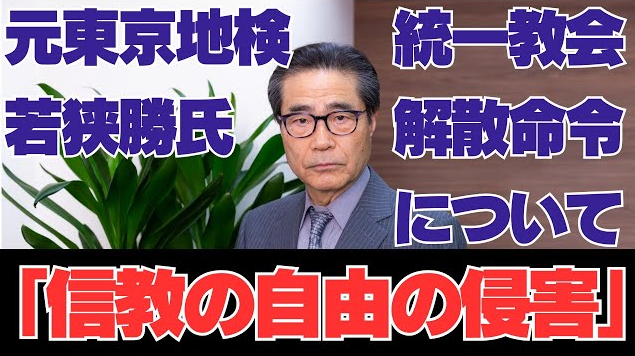要約(【信教の自由侵害】旧統一教会“解散命令”の法的問題点を若狭弁護士が解説)
元東京地検特捜部検事で衆議院議員も務めた若狭勝弁護士が、旧統一教会への解散命令の法的問題点を解説しています。
1. 法解釈の乱暴さ
- 解散命令は宗教法人法81条1号に基づくが、要件は
「法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」。 - 「著しく」「明らかに」と二重に強調されており、極めて重大かつ誰もが認める状況でなければならない。
- 今回の決定は、この厳格な基準を満たしているのか大いに疑問があると指摘。
2. 岸田政権による解釈変更(“朝令暮改”)
- 2022年10月14日の閣議決定では「刑罰法令に触れる行為」が要件とされていた。
- しかし翌19日、岸田首相は「民法上の不法行為」も含むと方針を転換。
- 背景には、世論・野党からの「統一教会対応が弱い」との批判に押され、政治的判断で解釈を拡大したとみられる。
- 若狭氏は「朝令暮改は法治国家にあってはならない。市民生活の自由を根底から脅かす」と批判。
3. 会社法との比較による不均衡
- 一般企業を解散させる会社法の規定は「刑罰法令違反」の場合のみ。
- より憲法で強く保障された宗教法人に対し、会社よりも緩い基準(民事の不法行為まで)で解散できるのは極めて不合理。
4. 政治的圧力と司法
- 小西洋之参院議員が岸田首相に「解釈を変えろ」と助言したとされ、その翌日に解釈が転換された。
- 総理と一議員の私的会話で法解釈が変わること自体、法治国家として大問題。
- また裁判所は省庁の主張に耳を傾けやすく、最高裁がすでに「民法の不法行為も含む」と認めていたため、今回の地裁判断にも影響があったと考えられる。
5. 若狭弁護士の結論
- 統一教会に過去に問題があったことは事実としても、それと法律解釈は別次元の問題。
- 解散命令の根拠は「粗雑かつ乱暴」で、法の安定性を損なう。
- 国民が「二世信者救済のためなら法解釈を曲げてもよい」と判断するなら仕方ないが、法律家としては「一事が万事」であり、今後の法秩序に重大な禍根を残すと警鐘を鳴らしている。
📌 核心ポイント
- 解散命令は「政治的圧力による法解釈変更」に基づくもので、法治国家の原則を逸脱している。
- 宗教法人に会社よりも不利な基準を適用するのは憲法上のバランスを欠く。
- 信教の自由を侵害する危険性が極めて大きい。