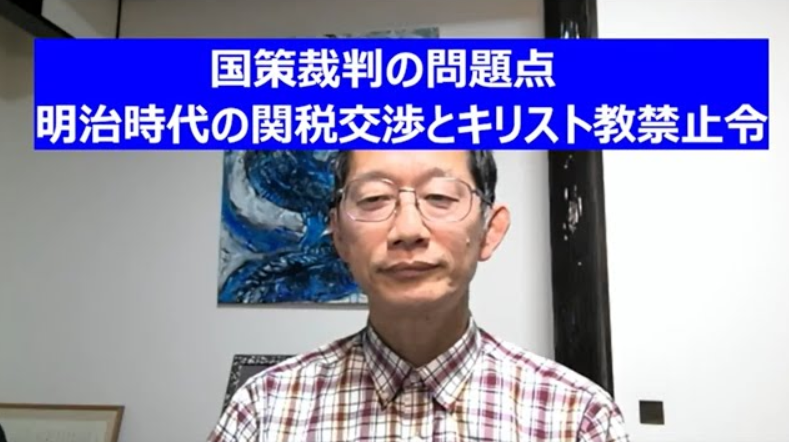国策裁判の問題点 明治時代の関税交渉とキリスト教禁止令【小笠原家庭教会】
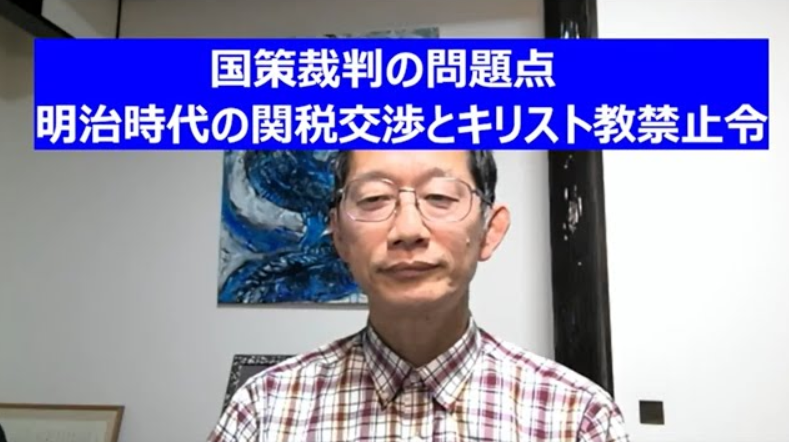
- 明治初期のキリスト教禁止令解除と関税交渉の関係
- 江戸時代、日本は約260年間にわたりキリスト教を禁止していた。
- 明治政府が不平等条約を改正するために欧米を訪問した際(1871年・岩倉使節団)、アメリカ側から「キリスト教を迫害している野蛮な国とは交渉できない」と拒絶された。
- これを受け、岩倉使節団は本国へ「キリスト教禁止を解くよう」指示。1873年(明治6年)にキリスト教禁止を象徴する高札が撤去され、キリスト教の禁制が正式に解除された。
- こうした宗教政策の転換は国際社会からの批判を和らげ、不平等条約改正交渉を進めるうえで不可欠な措置だった。
- 日本の関税自主権回復への歴史的経緯
- キリスト教禁止解除後、日本は「政教分離の方針」を示すことで国際的信用を得ようとし、1894年、陸奥宗光による日米通商航海条約の締結につながり、部分的な関税自主権が回復された。
- 現代の「総合関税」と信教の自由の関連
- 動画投稿者は、アメリカのトランプ前政権が日本を含む諸外国に対して総合関税をかける方針を示した点に注目。
- トランプ政権には新教の自由を保護する新局(Office of Faith-Based and Opportunity Initiatives)があり、その代表格としてポーラ・ホワイト牧師が活動。
- ポーラ・ホワイト牧師は家庭連合のイベントに参加し、韓鶴子(ハン・ハクチャ)総裁との交流があることから「日本国内で進む旧統一教会への強制的措置(解散命令等)が対米交渉(関税交渉)に影響を及ぼす可能性がある」と示唆している。
- 歴史は繰り返されるか?
- 明治初期と同様に、米国との交渉において「宗教の自由」に対する日本政府の対応が問題視される懸念を動画の中で指摘。
- 家庭連合への解散命令の動きが、対米関係・関税交渉など国際的な視点で影響を与えうると述べ、今後の展開を注目している。