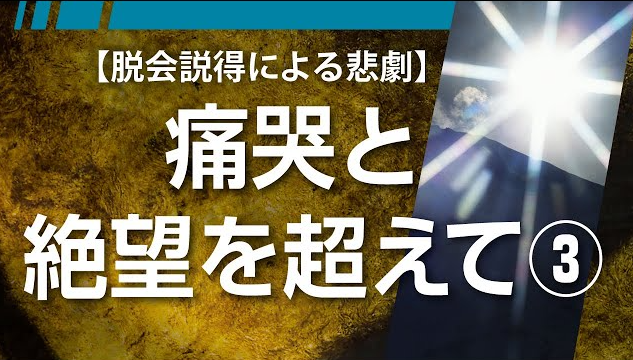目次
1. 背景と誘拐・監禁の経緯
- 出会いから献身まで
- 20歳で家庭連合と出会い、24歳で献身的に歩むように。
- 1988年10月、「6,500双祝福結婚式」に参加。
- 拉致監禁の準備
- 同じ信仰仲間の女性が脱会→反対牧師を紹介。
- 両親は反対牧師の指導を受け、約2年かけて密かに監禁場所を準備。
- 帰省時の監禁開始
- 1990年5月、祖母の墓参りに帰省する予定が一転、叔母宅に強制連行。
- 「徹底的に話し合うまで出さない」と宣告され、監禁が始まる。
2. 監禁生活の過酷さと精神の葛藤
- 隔離された空間
- 小部屋(お寺の裏)の天井低い室内に布団・ポータブルトイレ・机のみ。
- 窓や襖には釘・二重鍵で外界との接触を遮断。
- 精神的試練
- 「神を裏切ったら死ぬ」と自殺を覚悟し、刃物や頭痛薬を隠し持つ。
- 言葉も聖書も剥奪され、祈祷すら妨害される中で「自分の心」が最大の敵と感じる。
3. 霊的啓示と祈りによる支え
- 毎日の祈祷習慣
- 朝40分/昼21分/夜12分、必ず祈りを積み重ねる。
- 三つの啓示
- 「生きよ」:死を覚悟した自分に「生きて信仰を全うせよ」と告げられる。
- 「サタンの真の目的」:単に脱会させるだけでなく、祝福家庭を崩すことが狙い。
- 「願いのゆくえ」:地上に神の血統を残すことが自分の使命。
- 夢や映像からの励まし
- 牧師らの来訪を投げつけつつも、外国宣教者や映画(『大脱走』『最後の聖戦』)が「脱出」の象徴として力を与える。
- ある夜、「襖が開くから隣室へ逃げよ、窓から飛び降りよ」という夢を見て、脱出への確信を得る。
4. 40日目の脱出劇
- 釘の消失
- 脱出予定日の朝、なぜか襖の釘が外れ隙間が開いており、神の導きを実感。
- 脱走行動
- 昼休みの隙を突き、襖→障子→窓枠を外して脱走。
- 下にあった小川に飛び込み、裸足のまま走って近隣の民家に助けを求める。
- 教会への帰還
- 家庭連合の支援を取り次いでもらい、車で病院へ/タクシーで市内へ脱出成功。
5. その後の和解と歩み
- 家族との関係修復
- 親は最終的に「親は信じるものだ」と受け入れ、1992年に結納・披露宴を実現。
- 伝道活動への転回
- 傷を癒しながら、「まず遠くの人を愛す」姿勢で伝導対象者を御言葉で教育。
- 短期間でほとんどの担当者を教会につなげる成果を上げる。
まとめ
- 拉致監禁という極限状態でも、祈りと啓示を通じて「生きて信仰を全うする」決意を固め、40日間を耐え抜いて脱出に成功。
- 脱出後は家族と和解し、再び伝道の歩みに立ち、「傷を糧に人を愛しつなぐ」使命を果たしている貴重な体験談です。