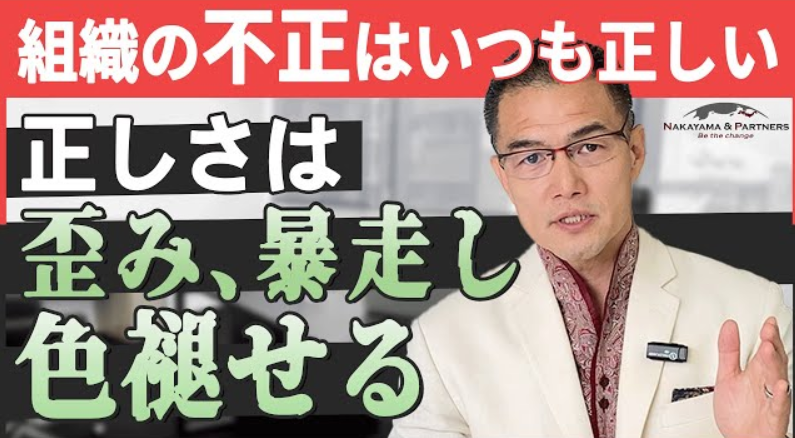目次
■ 講演の趣旨
「正しさ」や「ルール」は時代・文脈によって歪み、暴走し、人々を縛る危険性がある一方、真に大切なのは「美しさ(人の幸せ・善意)」である、というメッセージが主眼です。
■ 主なポイント
- 自己紹介と背景
- 湘南・大磯出身。野球に熱中し、東大法学部→弁護士へ。
- “死んだ後に何を心に残すか”を軸に、常に挑戦とリスクを取り続けてきた経験を紹介。
- 「正しさ」とは何か?
- 日本語の「正しさ(正義・倫理)」は、しばしば“美しさ”ではなく“ルール順守”を優先しがち。
- 西洋哲学的には「美しいこと(善、美、真理)」が本質であり、ルールはあくまで手段に過ぎない。
- 歴史が示す「正しさの暴走」
- 明治・昭和の国家政策(富国強兵、発行)や、ソ連の社会主義、ナチスの国家社会主義など、
過去の「正しい理想」が暴走・歪曲して大量の犠牲を生んだ事例を挙げる。
- 明治・昭和の国家政策(富国強兵、発行)や、ソ連の社会主義、ナチスの国家社会主義など、
- 具体例:法と人道のぶつかり合い
- 線路への飛び降り救助(ルール違反だが人命救助として称賛)
- ロボトミー手術(かつては最先端医療→後に非人道と評価)
- 原爆投下(アメリカでは“正しかった”とされる一方、日本では悲劇と認識)
- バンクシーの違法な落書きが“美術作品”と評価される現象
- 組織内の不正は「正しさ」の名の下に
- 企業や組織が“不正”を正当化するとき、多くは「社内規則」「上司指示」という“正しさ”を盾にする。
- しかし、ルールや礼儀を盲目的に優先すると、かえって害悪を助長する危険がある。
- 挑戦と失敗の価値
- 著者自身が「毎月1つ失敗をする」という目標を持ち、
失敗を恐れず挑戦し続ける姿勢こそが、本当の「生きる美しさ」を生むと提唱。
- 著者自身が「毎月1つ失敗をする」という目標を持ち、
■ 結論
- 「正しさ」だけに固執せず、常に背景や目的(人の幸せ、美しさ)を問い直す視点を持とう。
- ルール順守や倫理論だけに頼ると「組織の不正」を見過ごし、歪んだ正義に加担しかねない。
- 挑戦と失敗を通じて、自らの「美しく生きる意志」を周囲に残すことが真の価値である、という呼びかけで締めくくられています。