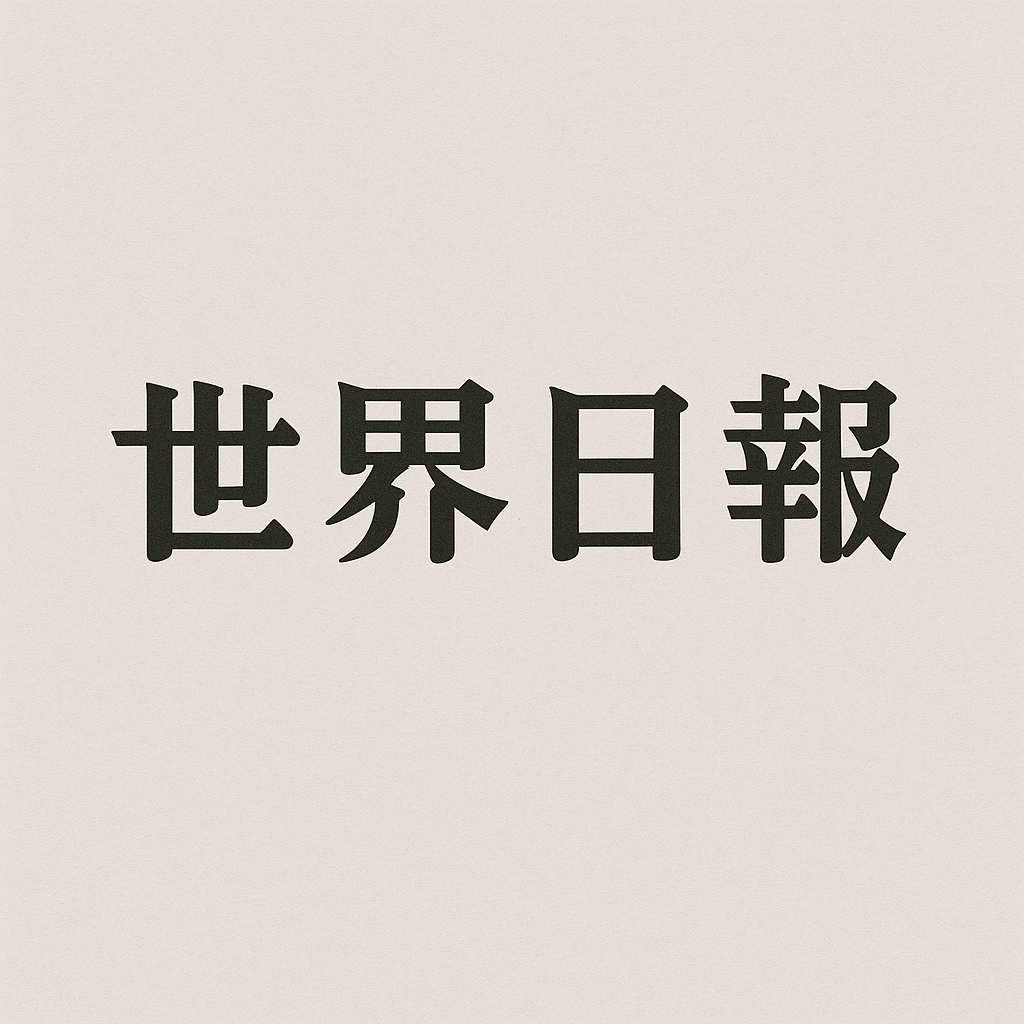目次
家庭連合解散命令に異議あり 推測で「継続性あり」は酷い(上)
/https://www.worldtimes.co.jp/society/20250818-198709/
有識者の意見について
- 書籍で 35人の識者が異議 を唱えたことは評価するが、まだ少ないと感じている。
- より多くの声が必要だと考えている。
東京地裁の解散命令決定(2025年3月25日)への評価
- 「法令違反かつ著しく公共の福祉を害した」との認定は ひどい決定 と批判。
- 家庭連合の 2009年コンプライアンス宣言以後の裁判は1件のみ。
- 以前の信者による訴訟を含めても 2件3名 に過ぎない。
- それにもかかわらず「看過できない規模の被害」と認定。
問題点の指摘
- 証拠裁判主義に反する判断
- 示談や和解を根拠に「不法行為」を「推測」や「想定」で認定。
- 「看過できない」という表現は不明瞭で、法的基準を欠く。
- 判例上も「想定・推測」で不法行為を認定した例はない。
- 継続性の認定の強引さ
- 30年前の被害を根拠に「今も同様の被害が続く」と断定。
- 「コンプライアンス宣言は弥縫策に過ぎない」と判断し、問題が残っていると結論づけた。
- だが「看過できない程度」との飛躍が強引で唐突。
- 最高裁決定との関係
- 2025年3月3日の最高裁は、文科省質問権事件で「民法上の不法行為も宗教法人法81条の『法令違反』に含まれる」と判断。
- これは 文理解釈を超えた拡張 で「法規範=法令」と無理やり結びつけた異常な判断。
- 地裁もこれを踏襲。
メディアと法律家への違和感
- 大手メディアは地裁決定を支持。
- 弁護士は全国に4万7000人いるが、異論を唱える声はほぼ皆無。
- 法律家として寂しく、異議がもっと表明されるべきだと指摘。
裁判所の解散審理の公開を “救済”と解散制度は無関係(下)
/https://www.worldtimes.co.jp/opinion/interview/20250819-198752/
声明と署名運動の意義
- 「宗教法人の解散について公平かつ公正な審理を求める」声明を発表し、署名運動を実施。
- 影響力の大きさは未知数だが、裁判に影響を与える可能性を期待して行っている。
- 文科省の陳述書偽造疑惑(約200人分)は徳永信一弁護士らが告発中。刑事捜査が進むのが理想。
- 裁判所も文科省提出の証拠の信用性を低く見るべきで、コンプライアンス宣言後の実態を無視しているのは不当。
非公開裁判の問題点
- 解散命令裁判が非公開なのは、非訟事件の建前(国家の後見的役割)が理由。
- しかし現代は行政手続も透明性が求められる時代。国と宗教団体が争う場面で裁判所の中立性を担保するには公開が憲法原理上の原則。
- 憲法学者・小林節氏も公開を主張している。
公開裁判へ向けた道
- 信者や職員が「利害関係参加」を主張している(徳永弁護士・小嶌希晶氏ら)。
- 原則公開の原理を活かし、当事者性のある信者が参加するのは当然。
- その他の公開のための法的手段も検討中。
集団提訴と世論操作の疑念
- この時期の二世信者による集団提訴は、高裁の抗告審を意識した世論形成と見られる。
- 本来なら安倍事件前にも提訴は可能。
- 二世の中には自殺遺族による慰謝料請求もあるが、原因は教義よりもメディア報道による影響が大きい可能性。
清算指針と資金への思惑
- 文科省の「宗教法人清算指針骨子案」は、残余財産を財団に移し賠償に充てる構想を提示。
- 霊感弁連は多額の賠償を得ることで弁護士費用の利益を狙っている面もあると指摘。
- ただし最高裁も2017年判決で「個々の被害者救済と解散制度は無関係」と明言。
- 被害者救済のためには、むしろ解散しない方がよいとも言える。
解散命令の本来の趣旨
- 解散制度はオウム真理教のように「治安を害し、将来取り返しがつかない被害」を抑止するためのもの。
- 現在の家庭連合が将来そのような脅威になるとは考えられない。
👉 全体を通じて、発言者は「解散命令の根拠が脆弱であり、非公開裁判や世論誘導の問題を正し、公開性・公平性を確保すべき」と強調しています。