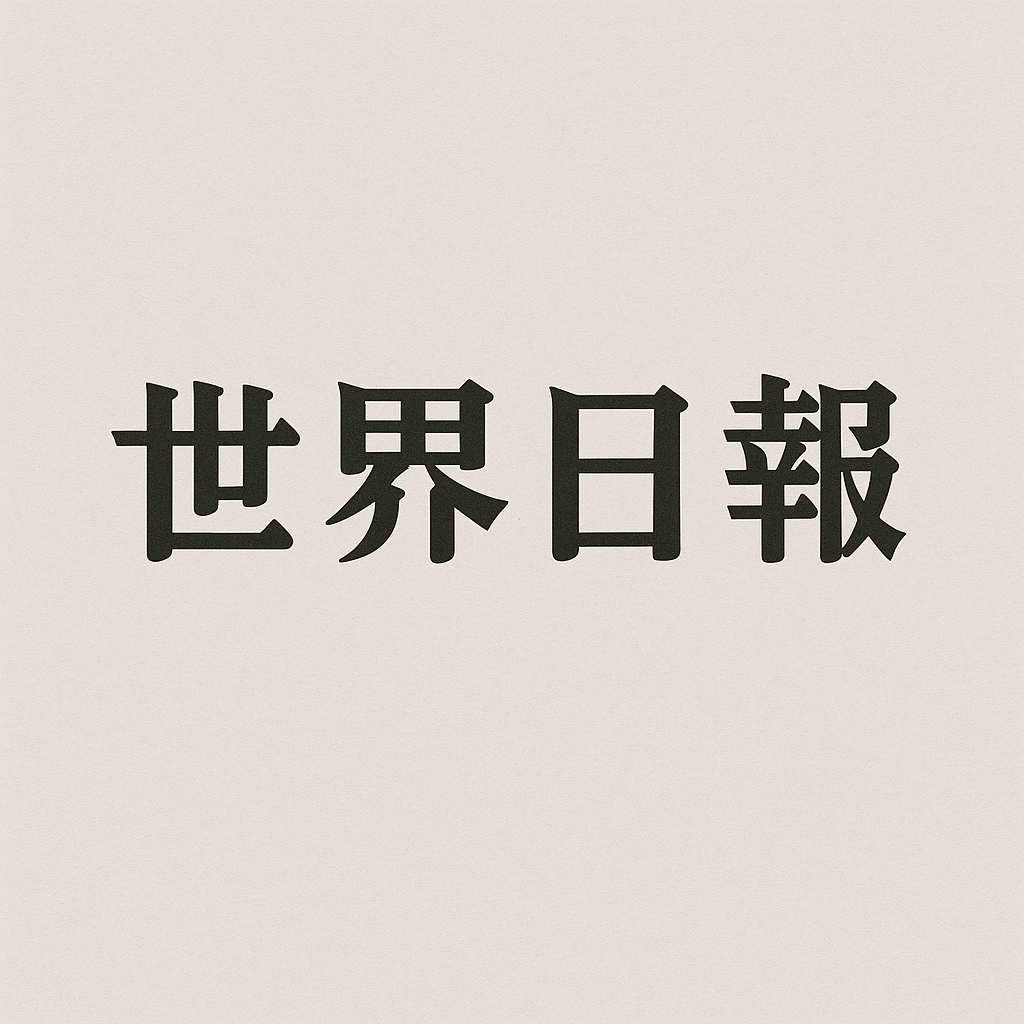https://www.worldtimes.co.jp/opinion/interview/20250902-199252/
ヤン・フィゲル元EU信教の自由特使インタビュー要約
(家庭連合解散命令への懸念)
目次
0. 背景
- 東京地裁(2025年3月25日):民法上の不法行為を根拠に家庭連合へ解散命令。
- 現状:家庭連合は即時抗告、東京高裁で審理中。
- 発言者:ヤン・フィゲル氏(元EU信教の自由特使、元スロバキア副首相)。
1. 解散命令への基本的評価
- 強い懸念:
- 憲法上の根拠を欠く。
- 国際人権規約(自由権規約)に違反。
- 影響:
- 少数派宗教への脅威となり得る。
- 一宗教への不当な措置は、他宗教への脅威に波及。
- 性質:
- 虚偽の証拠や告発に基づく。
- 法的根拠に乏しく、政治的動機が色濃い。
2. 東京地裁決定の問題点
- 恣意性・違憲性
- 非公開審理で透明性を欠く。
- 宗教法人法81条の拡大解釈:
- 本来「法令違反で公共の福祉を著しく害した場合」に限られる。
- これを元信者との32件の民事訴訟まで拡大解釈。
- 文科省が解釈を突然変更し、「公共の福祉への侵害」と認定。
- 基準の曖昧さ
- 「社会的相当性」「社会規範」など、曖昧で恣意的運用が可能。
- 国際的勧告との乖離
- 国連人権規約委員会は「公共の福祉」を理由とした制限を否定。
- 国家はむしろ宗教的少数派を保護する義務がある。
- 強制改宗問題
- 日本はプロテスタント牧師らによる**ディプログラミング(強制脱会)**を容認。
- 多くの原告自身が過去に拉致・隔離などの強制措置を受けていた。
- マインドコントロール理論の採用
- 非科学的な理論を前提に、「潜在的被害者」を想定して判断。
- → 偏向的で恣意的な判断。
3. 民主主義と法の支配への警告
- 正当な裁判は政治的圧力やメディアキャンペーンに左右されてはならない。
- 日本の民主主義の未来は:
- 法の支配の透明性
- 説明責任のある運用
- 人間の尊厳と公平な裁き
これらの擁護によってのみ築かれる。
4. 歴史的文脈(共産主義と宗教)
- 家庭連合解散運動の起源:日本共産党の反宗教的姿勢。
- マルクス主義無神論:宗教を排除しようとする思想。
- 宗教は国家権力や世俗的価値への従属から信者を解放するため、体制と衝突。
- フィゲル氏の経験:
- 共産主義体制下のチェコスロバキアで生活。
- 叔父は秘密警察に殺害された。
- 宗教は弾圧されたが、最終的に体制は1989年に非暴力で崩壊。
- 自由獲得運動の原動力は、キリスト教徒・カトリック教会だった。
5. 結論
- 家庭連合解散命令は、憲法違反・国際人権規約違反・政治的動機に基づく恣意的判断。
- 宗教的少数派を守ることこそが国家の義務。
- 日本は民主主義の根幹である信教の自由と法の支配を危機に晒している。