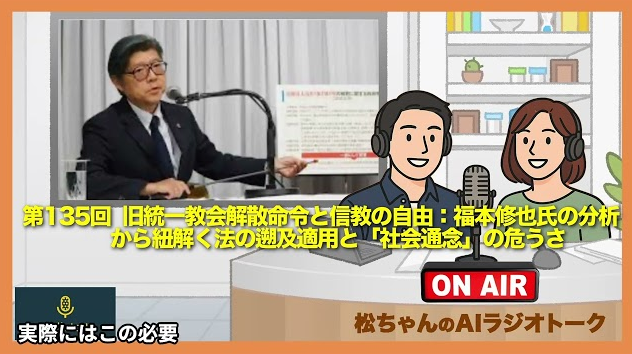要約します。
概要
動画は、福本修也氏の分析を手がかりに、家庭連合の解散命令申立てと信教の自由をめぐる法的論点を整理し、①法の遡及適用の疑いと②「社会通念」に基づく判断の曖昧さを中心に問題提起しています。
主要ポイント
- 国連勧告と「公共の福祉」
国連自由権規約委員会は、日本に対し「公共の福祉」の名で表現・宗教の自由を安易に制限しないよう勧告してきたのに、申立理由に同語が用いられている点を疑問視。 - 解散命令と信者の権利
東京地裁は「解散は法人格剝奪で、信者個々の宗教行為を直接禁止しない」としつつ、活動への事実上の支障は**「反射的利益の喪失」**に過ぎないと整理。
ただし解散には「必要かつやむを得ない」という高い基準が要るとしながら、実際の適用は形骸化しているのではないか、との批判。 - 法の遡及適用の疑い
地裁が違法性判断で参照した最高裁の基準は、2022年成立の“献金新法”の趣旨(寄付で生活破綻等への配慮)を取り込んだもの。
これを新法以前の行為に当てはめるのは、実質的に不遡及原則を揺るがすのではないか、という指摘。 - 「社会通念」基準の危うさ
「社会通念上、相当範囲を逸脱」という曖昧な概念を、基本権(信教の自由)を左右し得る判断に用いるのは恣意を招き、**自由権規約18条3項(法律による明確な制限)**に反するおそれ。
含意(動画の結論)
- 新法の考え方を過去に遡って適用したり、曖昧な「社会通念」に依拠する判断が前例化すると、他の団体(宗教・企業・NPO等)にも波及し、法的安定性と基本的人権の保障が損なわれかねない。
- 感情や世論ではなく、明確な法規範と厳格な基準に基づく審理が必要だ——と警鐘を鳴らしている。