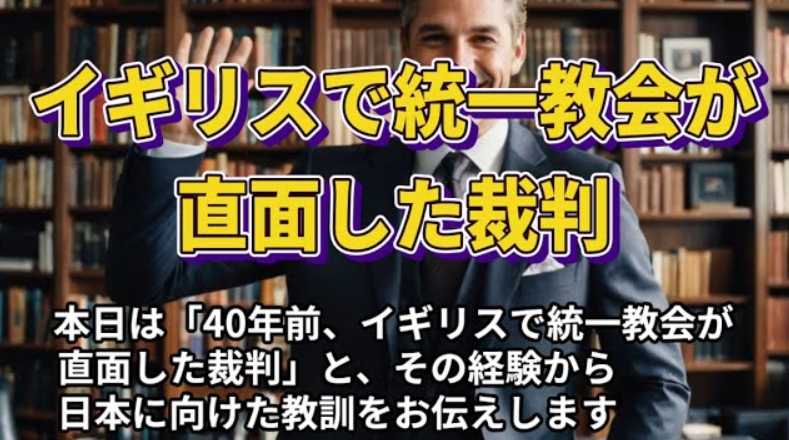目次
🔹背景(1970〜80年代)
- 1970〜80年代、イギリスの統一協会(現・家庭連合)はメディアから激しいバッシングを受ける。
- 1979年、大手新聞デイリーメールによる虚偽報道裁判で敗訴。
- これを契機に、英国政府は統一協会の宗教法人(チャリティ資格)を剥奪しようと動く。
- 1984年末、政府は「反社会的組織」とする証拠資料(約14,000ページ)を提示。
🔹裁判(1985〜1988年)
- 教会は弁護士チームを結成し、信徒の祈りと献身を背景に裁判に挑む。
- 証拠を精査すると、政府は「元信者や反対派の証言を鵜呑み」にしていたことが判明。
- 教会側は宗教学者アイリーン・バーカー博士の学術研究を提出。
- 元信者証言の矛盾を追及し、政府側の主張の信頼性を崩していった。
🔹劇的な結末
- 1988年、政府が突如訴訟を取り下げ。
- さらに教会側は約600万ドル(約10億円)の裁判費用補償を獲得。
- この勝利により、イギリスの反カルト運動は失速。
- 政府も「新宗教問題では学術研究を尊重する」姿勢へ転換した。
🔹勝利の理由
- 担当弁護士によれば「外的条件(法律・お金)だけでなく、信徒全体の祈りと献身(内的条件)が大きな力になった」と証言。
- 例:7日断食を終えた女性が「明日からまた7日断食する」と語るなど、強い信仰的雰囲気が裁判の背後にあった。
🔹日本への教訓
- 政府が一方の声(反対派や元信者のみ)に依拠して判断すると、やがて行き詰まる。
- イギリスの例は「長期的には真実が明らかになり、信教の自由が守られる」ことを示している。
- 現在の日本においても、冷静に歴史を見直す必要があると結論づけている。