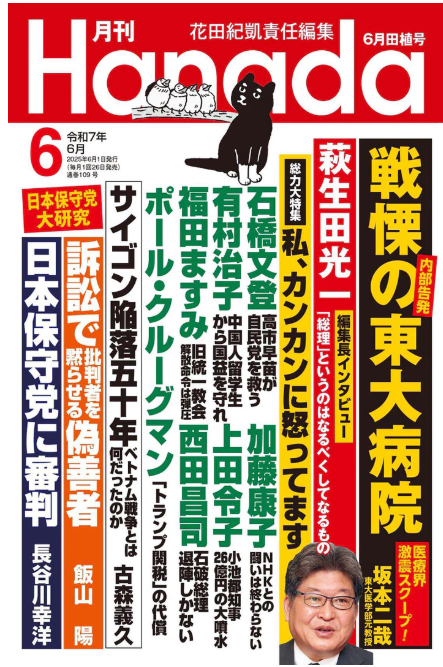目次
打ち砕かれた切実な思い
- 筆者は、旧統一教会(現在の家庭連合)に対する国家的な弾圧が、戦前の大本教弾圧に似ていると感じている。
- 戦前の第二次大本教事件では、一審で被告全員が有罪となったが、控訴審では不敬罪を除き、治安維持法違反容疑では全員が無罪となった。
- この控訴審を担当した高野綱雄裁判長は、大本教を「理路整然たる教義を持つ宗教」と認め、全員無罪の判決を言い渡した。
- 高野裁判長は、公平で名利にとらわれず、世間が騒がしい事件を無罪にする勇気を持った立派な人物と評価されている。
- 大本教の裁判では、一審の検事調書・予審判事調書の偽造が疑われ、これが控訴審の無罪判決に大きな影響を及ぼした。
- 現在の家庭連合の解散命令申し立て裁判の裁判長は鈴木謙也氏である。
- 鈴木裁判長は、文部科学省による家庭連合への質問権行使を適法と判断し、教団会長に過料10万円の支払いを命じた。
- この過料裁判で、宗教法人の解散事由である「法令違反」の対象に**「民法上の不法行為も含まれる」と判断**され、これはその後の高裁、最高裁でも維持された。
- 宗教法人解散要件に民法上の不法行為が含まれると国会で答弁したのは岸田前首相だが、その答弁内容を翌日あっさり翻した。
- 世界のほとんどの国では、信教の自由の重要性から、宗教団体の解散要件は刑事罰に限られている。
- 筆者は、過料裁判の一審判決時の鈴木裁判長による**「解散命令は信教の自由の重要性を踏まえ、慎重かつ厳格に判断されるべきだ」**という言葉に、一縷の望みを見出していた。
- 今年(執筆当時)1月になり、文部科学省による元信者の陳述書の虚偽、捏造疑惑が持ち上がり、裁判の流れが家庭連合側に傾くかと思われた。これは戦前の大本教弾圧時の調書偽造に類する行為と指摘されている。
- 筆者は内心、鈴木謙也裁判長を**「令和の高野綱雄」になぞらえたい**気持ちがあり、そう願っていたが、3月25日の解散命令のニュースによってその思いは打ち砕かれた。
まさしく国策裁判
- 家庭連合に解散命令が下された。
- 決定文は、家庭連合が宗教法人解散事由の「法令に違反し著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」という要件に当てはまると断じている。
- しかし、具体的に「誰が、いつ、どこで何を」し、「どの法令に違反した」のか、その基準も証拠も示されていない。
- これは杜撰な認定だが、宗教法人の解散命令申し立て裁判が非訟事件手続法に則って行われるため、手続き上可能となっている。
- 非訟事件では、刑事手続のような厳格な事実認定は要求されず、口頭弁論も必須ではなく、裁判は非公開で行われる。
- 過去に解散命令が出されたオウム真理教と明覚寺は、刑事事件で有罪が確定しており、客観的な証拠が揃っていたため、非訟事件であっても適切に判断できた。
- 家庭連合の場合、刑事事件は一件もない。
- 刑事事件ほど厳密な事実認定が要求されない民事事件のみで解散事由を認定することになり、非訟事件という曖昧な枠組みの中で、裁判官の恣意的な判断基準が入り込む余地が生まれる。
- 家庭連合にとっては、民事事件も解散事由に含まれるとされた時点で、この二重の構造・枠組みで相当に形勢不利だった。
- これはまさに国策裁判である。
国家が証拠を捏造
- 決定文には、法的にも常識的にも納得できない点が多々ある。
- 決定文には、文部科学省による元信者の陳述書の虚偽、捏造疑惑についての記述がほとんどない。
- かろうじて触れられているのは、「利害関係参加人(家庭連合)が個々の被害申告者の説明の信用性について指摘している点は、上記の認定を覆すに足りるものではない」という記述のみである。
- 家庭連合側は、虚偽・捏造が疑われる陳述書の数は多く、署名した覚えがない、他の宗教の信者のものが混じるなど手口は悪質で、文科省の職員が組織的に関わっていたことは間違いないと主張する。これは一部の例外ではなく氷山の一角だという。
- 文科省による捏造は、前年(執筆当時)の秋頃には発覚しており、12月末の元信者への証人尋問で事実がより一層明白になった。
- 文科省側は法廷で一切反論できず、黙っていた。
- 国家が証拠の捏造をすることは到底許されないと、家庭連合側の弁護士である福本修也氏は怒りを露わにしている。
- 鈴木裁判長は、虚偽・捏造が明らかになったため、文科省が集めた元信者261名の陳述書の全てを証拠として採用しなかった。
- 国家公務員がこのような不正に手を染めたのは、他に有力な証拠がなく、彼らが焦ったためとしか考えられない。
示談や和解まで「不法行為」
- 裁判所は、家庭連合が敗訴した32件の民事裁判だけでなく、裁判前の示談や判決前の和解までも「不法行為」として括り、「膨大な規模の被害を生じさせ、いまもなお看過できない程度の被害が残存している」と認定した。
- 通常、示談や和解は法律に則って解決金が払われるものであり、「不法行為をした」とは認定されない。
- 家庭連合によれば、献金は自由意思だったが、経済状況の変化による返金要求や、全国弁連による架空の事実に基づく請求に対し、教団側に反証可能な証拠がないため、やむなく返金に応じたケースがほとんどだという。
- そうしたケースまで、十把一絡げにすべて不法行為であると推測されたのは、およそありえないことである。
- 32件の民事裁判についても、これらが不法行為と認定された理由、根拠には大きな疑問がある。
全国弁連の法廷戦術
- 決定文は、過去の民事判決において、献金勧誘等行為に「怨恨を持つ霊の因縁」などによる不幸から脱するために解怨が必要だと説かれ、その結果献金や物品購入をしたという共通の**「類型的な傾向」**が見られるとしている。
- つまり、原告は霊や地獄の説明で脅されて献金・物品購入をしたと主張し、それが認められて勝訴したとしている。
- しかし、これらの原告の過半数は、脱会屋やキリスト教牧師に唆された親族によって拉致監禁され、強制的に棄教させられた元信者たちである。これは元信者自身が過去の民事裁判で告白している。
- 元信者たちは、拉致監禁を避けるためにやむを得ず教団を提訴し、その際に**「マインドコントロールによって入信させられ、先祖の霊や地獄などの脅し(畏怖誤審)で献金させられた」**という主張を持ち出す。
- 大人が脅されて献金すると主張するのは無理があるが、宗教を知らず教団に偏見を持つ判事らはこれを容易に信じて判決を下す。
- これは、元信者の代理人を独占的に務めている全国弁連の弁護士たちが編み出した法廷戦術である。
- 献金訴訟の記録を読むと、原告側はこの畏怖誤審を金太郎飴のように主張している。
- 筆者は**「いい大人が脅されて献金するなどありえない」**と繰り返し述べている。取材した高額献金者も同様に「脅されたら教会をやめている」「家系図を見せられてここが悪いと言われたら怒る」と強調している。
拉致監禁事件を完全無視
- 信者が献金するのは、世界平和への貢献、共産主義との戦い、地上に神の国を作るという教義への共鳴など、純粋な信仰上の動機が圧倒的である。
- 教団側は、1966年から日本全国で広範囲に行われ、4300人以上の被害者が出た拉致監禁事件や、これにより棄教させられた元信者たちの虚偽の証言が解散命令請求の根拠になっていることを多数の資料を用いて説明した。
- しかし、決定文はこれを完全に無視している。
- 現役信者らは、自身が自由意思で献金したことを証明する陳述書や自身の献金動機を述べた陳述書を提出している。
- しかし、裁判所はこれらの現役信者の証言、供述を**「教団側のコントロール下にあるので、正しい供述は期待できない」といった偏見と思い込みから認定に採用しなかった**。
- 家庭連合法務局副局長の近藤徳茂氏は、西欧の学会では背教者の証言に信憑性がないという定説があるが、日本の裁判所はこれを知らず**「被害者」の証言を偏重した**と述べている。
- こうした不公正な認定によって得られた過去の民事判決を、解散事由判断の証拠とすべきではないと近藤氏は主張する。
共産党も創価学会も解散か
- 過去を何十年も遡って不法行為を認定している点も問題であり、この理屈ならどんな組織、団体も引っかかる可能性がある。
- 例として、日本共産党の宮本顕治による暴力致死事件、武装闘争路線、テロ活動、騒乱事件などが挙げられている。
- 創価学会についても、公職選挙法違反事件、言論出版妨害事件、盗聴事件、多数の民事訴訟などが挙げられている。
- 拉致監禁を主導した牧師が多いとされる日本基督教団についても、内ゲバや、大学会議室への侵入・監禁・脅迫事件などが挙げられている。
- これらの他団体の事件に比べれば、家庭連合の献金問題は基本的に教団内部のトラブルに過ぎず、大部分は解決済みである。
- それにもかかわらず、国や司法が出てきて解散命令を下すのは異常としか思えない。
- 教団側は、解散事由の「公共の福祉」、「社会通念」、「社会的相当性」といった広範で曖昧な概念を用いることは国際法に違反していると主張した。
- 国連の自由権規約委員会が日本政府に3度、「公共の福祉」概念で宗教的表現の自由を制約しないよう勧告したが、日本政府はこれを無視した。
- 裁判所もまた、政府に倣ってか、この国際法違反の事実を無視し、決定文では一言も触れていない。
- 今回の裁判の大きな焦点の一つは、2009年のコンプライアンス宣言以降の教団の改革成功と、霊感商法被害や高額献金訴訟の激減を裁判所がどう評価したかである。
- コンプライアンス宣言以降、献金裁判や示談件数は激減しており、最近12年間は裁判所で献金の違法性が認定されていない。
- 決定文でも「顕在化している被害申告の数は減少が続き、近時における被害申告の数は相当に減少している」と認めている。
- それにもかかわらず、決定文は「潜在的な隠れた被害が『相当程度』あることが『想定される』から」問題状況は看過できない程度に残存している、という推論に推論を重ねた判断を示した。
- これは、解散という結論を導くための強引なレトリックであり、こじつけ、難癖の類である。
- 教団への解散命令は、刑事事件を引き起こした他の宗教法人への扱いと比較して、著しく公平性を欠いている。
- 過去に教祖や幹部が強姦、わいせつ、暴行致死、心霊療法致死などの事件を起こしても、解散命令が出されなかったり、有罪判決を受けても解散命令請求も質問権行使も行われない宗教法人がいくつもある。
- こうした現実を見ると、**「なぜ家庭連合だけが?」**という疑問に突き当たらざるを得ない。
取り返しのつかない事態に
- 結局、裁判所は法理論、憲法、国際法、国連勧告を無視し、新しい違法性認定基準を過去に遡及させ、推測に次ぐ推測という手法によって不法行為を認定し、これを根拠に解散命令を下した。
- この決定は、政府と偏向したメディアに煽られた世論に迎合した、結論先ありきの不当判決であると、家庭連合法務局副局長の近藤徳茂氏は憤る。
- 消費者庁の文書によれば、近年の家庭連合に関する消費生活相談件数はごくわずかであり、顕在化していない不法行為など存在しないと近藤氏は主張する。
- 解散命令が確定すれば、家庭連合の職員約2000名(扶養家族含め約4000名)が解雇され、再就職は困難である。
- 10万名を超える信者は社会的差別と迫害を受けているが、解散が確定すれば状況が悪化し、取り返しのつかない人権侵害が生じることが見えている。
- 決定文には、こうした信者の苦境を考慮した形跡が一切なかった。
- 全ては2022年7月8日の安倍元首相暗殺から始まった。あの事件がなければ、家庭連合が解散に追い込まれることはありえなかったとしている。
- その後、日本は政治もメディアも、そして司法までがテロリスト山上徹也の願望をかなえる形で動き、これを実現させた。
- 裁判所まで魔女狩りに加担するようでは、法治国家として末期的症状である。
- 国家による虚偽陳述書の捏造を黙認・隠蔽して解散命令を下すなど、歴史に拭いがたい汚点を残す。
- 家庭連合側は、抗告審に向け引き続き正攻法で闘うしかないと考えている。
- 法律家としての良心と矜持を持ち、虚心坦懐に真実と向き合う判事がいることを期待している。
- 筆者は再び**「令和の高野綱雄裁判長出でよ!」**と願うしかないと結んでいる。