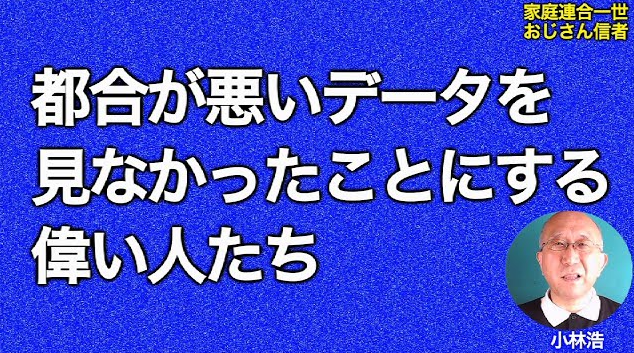都合が悪いデータを見なかったことにする偉い人たち【家庭連合一世おじさん信者】
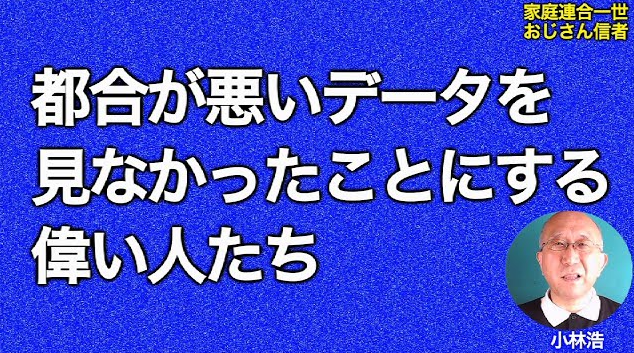
「都合が悪いデータ」を隠したミリカンの電気素量実験
- ミリカンは電気の最小単位(電気素量)を測定する実験で170個のデータを得た。
- しかし論文には「整数倍でない」112個を除き、仮説に合う58個だけを掲載。
- 自分の仮説を証明するために、都合の悪い観測結果を「誤差」として排除した例。
常識に反する発見を拒絶したガリレオと大学教授たち
- ガリレオは自作の望遠鏡(約33倍)で月や太陽の表面の凹凸・黒点を観測。
- 教授たちは「天は完璧な球体」という宗教的常識に縛られ、観測結果を否定。
- 地上観測だけは認めたものの、天体観測は「望遠鏡の誤作動」とみなして排除した事例。
科学にも主観が介在する構造
- 実験・観測前にある「仮説」がデータ選択に影響し、都合の悪い結果は切り捨てられがち。
- 科学者も人間であり、信念や常識(主観)から自由ではない。
- データは理論を補強する道具にも、矛盾を隠す手段にも成り得る。
客観性を超える「信念」の力
- 優れた観測技術でも、「信じたい世界観」が勝ると新知見は認められない。
- 科学的事実も、理論(主観)に裏打ちされて初めて「実在」と見なされる構造がある。
- 真実を追求する姿勢と同時に、自身の先入観を自覚することが不可欠。