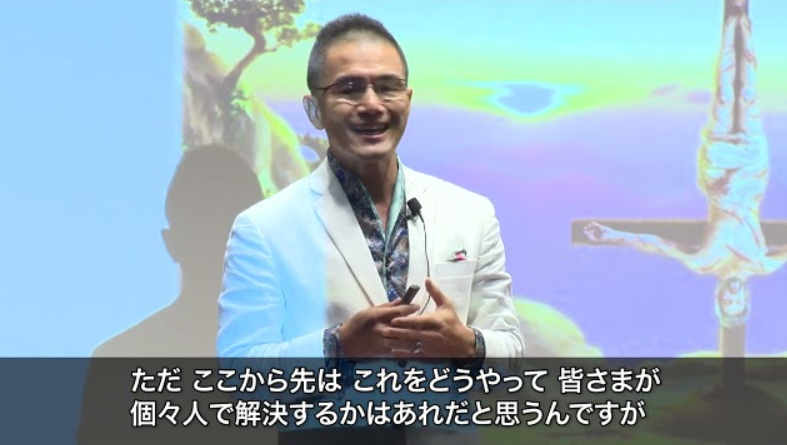目次
■ 講演の構成と背景
- 講演者プロフィール
- 東京大学法学部卒、シンガポール国立大大学院修了
- 中山国際法律事務所代表、グローバルチャレンジ理事長
- 個人的体験への言及
- 拉致監禁被害者のPTSD・家族の絶望、講演者自身の「娘を奪われた」ケースを紹介
- 被害者の裁判提起が「心のリハビリ」として果たす役割
■ 拉致監禁の背景と構造
- “大場仏教”的エネルギー
- 「世直し」を掲げる宗教運動が、世俗との摩擦を引き起こしやすい(土壌学的に過剰な信仰心)
- 古代キリスト教の殉教例や戦前の国策運動との類似を指摘
- 拉致監禁→裁判提起のサイクル
- 1980〜2000年代にかけて、高齢信者を中心に高額寄付返還訴訟が急増
- これら被害訴訟は当事者の「リハビリ」「自己肯定」機能を担い、民事裁判の累積が現在の解散請求論にも影響
■ 法的論点:拉致監禁は「違法」
- 正当行為・緊急避難のいずれにも該当しない
- 拉致監禁は「暴行罪」かつ「不法監禁罪」にあたり、救命・自己防衛の範囲を超過
- 4万5,000人の弁護士間で反論者は皆無と断言
- 濫用される「親の方針」と教団責任の混同批判
- 「親が信仰に基づき子を監禁した」として教団全体に責任を押し付けるのは法理・常識双方から無理筋
■ 主要データと現状分析
- 訴訟件数と主体
- 過去35年で約4300人が拉致監禁→原告化。多くの訴訟で霊感商法弁護団(霊感弁ITU)が代理
- 消費者庁では98%が霊感商法相談、教団関連は残り2%に過ぎない事実(弁護団はこれをほぼ無視)
- 時効・権利消滅問題
- 20年以上前の寄付返還請求が全体の25%を占め、法的に権利消滅しているケースが多数
■ なぜ「拉致監禁」が知られにくいのか
- 被害者の告訴・裁判提起のハードル
- 親や家族を訴える苦痛、職場・地域での偏見
- 警察・メディアの優先順位
- 殺人・横領事件に比べ、家庭内の事件は後回しにされがち
■ 結論と今後の課題
- 法律的結論:拉致監禁に解散請求要件は存在せず、法的に正当化不能
- 社会的提起:
- 「空白の30年」を超えた今、拉致監禁問題を冷静に再検証すべき
- 当事者間・社会との対話を継続し、法と人権の視点で成熟した対応を進める必要