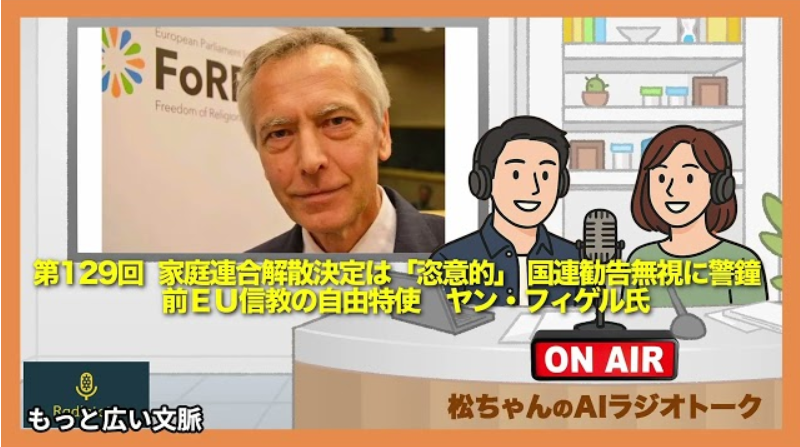要約:「家庭連合解散命令は恣意的」―ヤン・フィゲル氏の警告
元EU信教の自由特使 ヤン・フィゲル氏 が、日本の家庭連合(旧統一教会)への解散命令決定について、国際的な人権基準の観点から強い懸念を表明しています。
1. 法的根拠と国際規約違反の疑い
- 東京地裁の決定は、日本国憲法上の根拠を欠き、さらに自由権規約(ICCPR)違反の可能性があると指摘。
- 特定の宗教団体だけでなく、他の少数派宗教やマイノリティへの波及リスクを警告。
2. 恣意的な判断の懸念
- 裁判が非公開で行われており透明性に欠ける。
- 宗教法人法81条の解釈を拡張し、32件の民事判決を積み重ねて「公共の福祉を著しく害した」と判断したことを問題視。
- 「公共の福祉」という抽象的な理由で自由を制限するのは、国連の勧告に反する。
3. 強制改宗(ディプログラミング)の黙認
- 元信者の中に強制的な改宗措置を受けた人が多いことを指摘。
- 日本政府がこれを容認してきたのは、少数派宗教を保護する義務を怠った証拠だと批判。
4. マインドコントロール理論の採用
- 科学的根拠に乏しい理論を裁判所が用い、実証されていない潜在的被害まで考慮した判断は偏っていると主張。
- 背景には政治的動機やメディアキャンペーンの影響があると見る。
5. 歴史的背景と信教の自由の意義
- フィゲル氏は共産主義下での弾圧経験から、宗教が人間の尊厳と自由を守る力を持つと確信。
- 信教の自由は「すべての人権のリトマス試験紙」であり、内面の自由(フォーラム・インターナム)は絶対に侵害されない。
6. 国際社会の反応と日本への要請
- 国連人権規約委員会は、日本に「公共の福祉」を理由とした制限をやめるよう勧告してきた。
- 国連特別報告者ナジラ・ガネア氏が訪日調査を希望しているが、日本政府は受け入れていない。
- 日本は国際対話を拒否せず受け入れるべきであり、アメリカ政府の介入・対話にも期待が寄せられている。
7. 結論
- 家庭連合解散命令は手続きの透明性・法解釈の公正性を欠き、恣意的に見える。
- 確定すれば、日本の民主主義や国際的信頼性を大きく損ない、他の少数派宗教への脅威となる。
- 21世紀の日本が、20世紀のヨーロッパの迫害の過ちを繰り返してはならないと強く警告している。