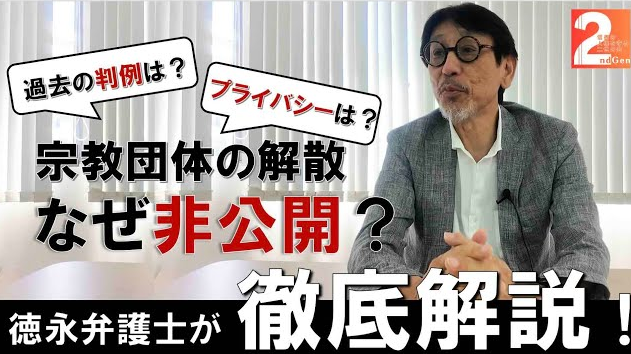動画要約
タイトル: 【解説】徳永弁護士が皆さんの質問に答えました!
1. 非公開審理の問題点
- 宗教法人法81条では解散命令請求が「非訴事件」として扱われ、原則非公開。
- しかし憲法32条(裁判を受ける権利)、82条(公開裁判の原則)に照らすと矛盾がある。
- 公開されないことで証拠の捏造・偽造の可能性や、被告側が反対尋問できない問題が発生する。
- 徳永弁護士は「公開が原則であるべき」と主張。プライバシー保護は82条2項の例外規定で対応可能。
2. AIの説明に対する反論
- AIは「社会的影響が大きい・証言者確保のため非公開が必要」とするが、徳永弁護士は「それは裁判の否定」だと指摘。
- 裁判の本質は公開の場で証拠を吟味し、反対尋問を通じて真実を浮かび上がらせることにある。
3. 過去の判例・学者の意見
- 昭和35年、最高裁が「非訴事件での扱いは憲法違反」との判決を出した例がある。
- 憲法学者・小林節氏も「大問題」と指摘し、意見書を執筆。国際的にもビターウィンター誌で紹介された。
4. 利害関係人参加の意義
- 「8人が参加すると無限に広がるのでは」との質問には、人数の多寡ではなく「公開性を高めるための意味」が重要と回答。
- 信者が参加することで「捏造証拠を出せなくなる」抑止効果も期待できる。
5. 国際的注目
- 家庭連合(旧統一教会)は世界的な組織であり、日本での解散命令は国際社会でも驚きをもって見られている。
- 宗教の自由は人権の基礎であり、その裁判が非公開で行われるのは国際的な常識から外れている。
まとめ
徳永弁護士は、宗教法人解散命令を「非公開審理」で行うことは憲法違反の疑いが強いと指摘。公開裁判の原則を守らなければ証拠捏造のリスクが高まり、信者の権利も侵害されると警鐘を鳴らした。過去の最高裁判例や憲法学者の意見を根拠に、利害関係人参加を通じて公開性を確保しようとしている。さらに、この問題は国際的にも注目を集めており、日本の司法の透明性が問われている。