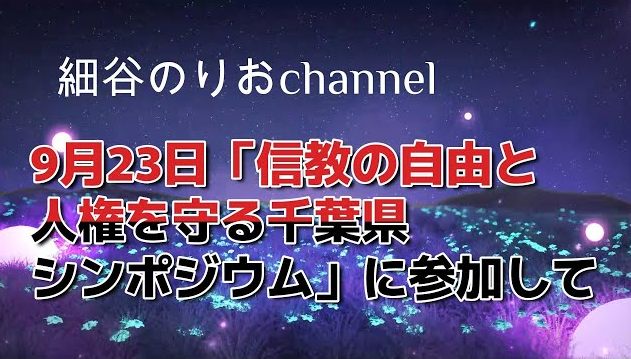要約:「信教の自由と人権を守る千葉県シンポジウムに参加して」
このシンポジウムの講演では、なぜ今「信教の自由を守れ」と声を上げなければならないのかが語られました。背景には、岸田内閣・文科省による家庭連合への解散命令請求があり、裁判でその是非が争われている点が強調されています。
1. 憲法と信教の自由
- 日本国憲法20条で保障されている「信教の自由」が、家庭連合の解散命令請求によって脅かされていると指摘。
- 解散には「悪質かつ継続的な法令違反」「著しい公共の福祉の侵害」が必要だが、家庭連合には該当しないと主張。
2. 家庭連合の実態
- 3年間の交流や観察を通じて、家庭連合はむしろ社会に良い活動をしている団体だと評価。
- 解散に値する証拠や事実は見当たらない。
3. 議会での経験
- かつて砺波市議会で「統一協会との関係調査」を求める請願が出たが、事実確認では被害実態が認められなかった。
- 結果、共産党議員以外は全員が反対。全国で同様の冷静な議論があれば、今日の問題は起こっていなかったと述懐。
4. 東京地裁での敗訴と課題
- 家庭連合は「32件の事件は民事事件だから解散に当たらない」とだけ主張し、個別事件の実態に踏み込まなかった。
- そのため東京地裁で敗訴したが、問題点は明確であり高裁で修正可能だと説明。
5. 高裁での展望
- 現在は32件を一件ずつ精査し、実際の被害があるのか徹底的に検証している。
- 特に「過大請求を繰り返した弁護士による訴訟」などの不当性を指摘。
- 高裁では被害者の声だけでなく、家庭連合側の証人尋問も認められ、10月に実施予定。
- これが最大の山場となる。
6. 市民への呼びかけ
- 裁判は非公開で不透明だが、日本の裁判は最終的に公正な結論を出すと信じている。
- 信教の自由と人権を守る運動を続けてほしいと訴えて結んだ。
👉 要するに、講演者は「家庭連合に解散命令を下す根拠はなく、裁判で正当性は必ず認められる」と強調し、市民に対して「信教の自由を守る活動を継続するように」と呼びかけています。